|
定番「3DグラフィックスAPI」の基礎知識と使い方
|
DirectX 11 3Dプログラミング [改訂版]
|
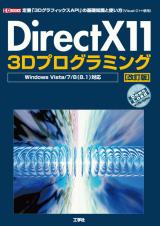
|
大川 善邦・大澤 文孝・成田 拓郎 共著
2015年 5月15日発売
B5判
368ページ
定価 ¥3,080(本体 ¥2,800)
|
|
ISBN978-4-7775-1894-4 C3004 ¥2800E
|
 |
≪Windows Vista/7/8(8.1)対応!≫
「DirectX」は、Windowsのマルチメディアアプリ向けの拡張API群。
「DirectX11(Direct3D 11)」は、「Windows Vista/7/8」上で動作し、「シェーダ・モデル5」「本格的なテッセレーション」「DirectCompute※」のサポートなど、グラフィックス機能が大幅に強化されました。
これらの機能を活かすには、「DirectX11対応」のビデオカードが必要ですが、すでに多くの対応ずみビデオカードが、AMDやNVIDIAから発売されています。
本書は、DirectXの開発環境である「Visual Studio」(Visual C++)を使って、「Direct3D 11」の基本的な知識とプログラミング方法を、初歩的なレベルを中心に解説したものです。
※ 「Windows Vista」「Windows 7」「Windows 8.1」上で、「OpenCL」やNVIDIAの「CUDA」などのシェーダプログラムを動作させるAPI。
|
|
| ■ 主な内容 ■ |
|
はじめに
プロローグ
| [1] DirectXの誕生 |
[2] 新しい出発 |
| [3] そして未来へ |
|
| [1] 「DirectX11」開発に必要な環境 |
[2] 「DirectX SDK」のダウンロードとインストール |
| [3] 「DirectX11 Sample Browser」で動作確認する |
[4] 「Visual Studio 2010」でのビルド方法 |
第2部 実践編
| [1]特徴 |
[2]構成 |
| [3]リソース |
[4]APIのレイヤー構成 |
| [5]ヘルパー・ライブラリ |
[6]開発環境 |
| [7]実行環境 |
|
| [1]プロジェクトの作成 |
[2]DirectXのエラー表示機能 |
| [3]アプリケーションの基本構造 |
[4]使用する「機能レベル」の決定 |
| [5]デバイスとスワップ・チェインの作成 |
[6]バック・バッファの設定 |
| [7]深度/ステンシル・バッファの設定 |
[8]画面の描画 |
| [9]デバイスの消失 |
[10]終了処理 |
| [11]サンプル・プログラム |
|
| [1]DXGIについて |
[2]グラフィックス環境の調査 |
| [3]ウインドウ・サイズ変更時の処理 |
[4]ウインドウ・サイズの変更 |
| [5]無駄な画面描画の抑制 |
[6]画面モードの切り替え |
| [7]トーンカーブによる階調補正 |
|
| [1]ベクトルの変換操作 〜行列と同次座標〜 |
[2]左手座標系と右手座標系 |
| [3]三角形ポリゴンと向き |
[4]3Dグラフィックスの座標系と座標変換 |
| [5]照明(光源と反射) |
[6]16ビット浮動小数点数 |
| [7]クオータニオン |
[8]平面 |
| [9]色 |
[10]その他の「定数」「マクロ」「関数」 |
| [1]描画手順の概要 |
[2]ステート・オブジェクト |
| [3]描画パイプラインで行なう処理 |
|
| [1]プリミティブの種類 |
[2]頂点バッファとインデックス・バッファの用意 |
| [1]シェーダ・ステージの概要 |
[2]シェーダで実行するコード |
| [3]HLSLコードのコンパイル |
[4]シェーダ・オブジェクト |
| [5]定数バッファ |
[6]シェーダ・コンパイラ「fxc.exe」 |
| [1]入力アセンブラの概要 |
[2]「頂点バッファ」と「入力スロット」 |
| [3]入力レイアウト・オブジェクト |
[4]プリミティブの種類 |
| [1]ラスタライザの概要 |
[2]ラスタライザ・ステート・オブジェクト |
| [3]ビューポート |
[4]シザー矩形 |
| [1]出力マージャーの概要 |
[2]描画ターゲット |
| [3]ブレンド・ステート |
[4]深度/ステンシル・ステート |
| [1]描画手順 |
[2]定数バッファへの書き込み |
| [3]描画パイプラインを構成 |
[4]描画 |
| [5]サンプル・プログラム |
|
| [1]HLSLの基本的な文法 |
[2]HLSLの組み込み関数 |
| [1]シェーダ関数の概要 |
[2]頂点シェーダ関数 |
| [3]ジオメトリ・シェーダ関数 |
[4]ピクセル・シェーダ関数 |
| [5]システム生成値 |
[6]サンプル・プログラム |
| [1]テクスチャ |
[2]画像ファイルから「シェーダ・リソース・ビュー」を作る |
| [3]画像ファイルからテクスチャ・リソースを作る |
[4]描画ターゲットになるテクスチャ・リソースを作る |
| [5]CPUから書き込むテクスチャ・リソースを作る |
[6]テクスチャを画像ファイルに保存する |
| [1]テクスチャの定義 |
[2]サンプラを使わないテクスチャ読み込み |
| [3]サンプラを使ったテクスチャ読み込み |
[4]サンプル・プログラム |
| [1]3Dデータの形式について |
[2]Wavefront OBJファイル形式 |
| [3]Wavefront OBJファイル読み込み関数 |
[4]XNA Collisionライブラリ |
| [5]描画用データの作成 |
[6]サンプル・プログラム |
| [1]「複数インスタンス」とは |
[2]インスタンス描画メソッド |
| [3]各インスタンスの描画設定 |
[4]サンプル・プログラム |
| [1]キューブ・テクスチャの概要 |
[2]キューブ・テクスチャへの描画 |
| [3]「キューブ・テクスチャ」へのアクセス |
[4]サンプル・プログラム |
| [1]ストリーム出力の概要 |
[2]バッファ・リソースの作成 |
| [3]ジオメトリ・シェーダの作成 |
[4]ストリーム出力を使った描画パイプラインの実行 |
| [5]サンプル・プログラム |
|
| [1]「影」について |
[2]「シャドウ・ボリューム」を使った影 |
| [3]「シャドウ・マッピング」による「影」 |
|
| [1]「コンピュート・シェーダ」について |
[2]「コンピュート・シェーダ」のコード |
| [3]デバイスの作成 |
[4]シェーダの作成 |
| [5]リソースの作成 |
[6]「シェーダ・リソース・ビュー」の作成 |
| [7]「アンオーダード・アクセス・ビュー」の作成 |
[8]「コンピュート・シェーダ」を使った演算 |
| [1]PIXの基本的な使い方 |
[2]レンダリングの確認 |
| [3]描画するメッシュの確認 |
[4]シェーダの動作確認 |
付録[1] Direct3D 11対応グラフィックス・カード
付録[2] サンプルファイルのダウンロードについて
索引
|
本書内容に関するご質問は、こちら
本書のサポートページはこちら.
|
 |

|








